はじめに
ここで述べるビジネスモデル特許とは「IT(情報技術)を活用して実現したビジネス方法を対象と
した特許」という狭義の意味である。このビジネスモデル特許が日本でも昨年から新聞等などのメデ
ィアにて話題となっている。話題になる理由に日本ではIT化が近年著しく進むにつれ、ソフトウェア
の応用やWebでのビジネスが増え、その中でのビジネス上のアイデアに対して特許が取れるようにな
ったこと、これまでの特許とはあまり関係の無かった金融、広告業界などのサービス業も注目してい
ること、ビジネスモデル特許は目にみえないシステムやアイデアに特許を与えることに対して多くの
問題点があること等が挙げられる。私はこの新しい形の特許に対して日本は、また日本企業はどう受
け止めて取り組んでいくのか、そしてビジネスモデル特許が抱える多くの問題点に着目し、事例を含
めながら考察する。
1 ビジネスモデル特許とは
特許とは「産業上利用できる発明」を保護するために出来たものである。今まではその発明の中にビ
ジネス方法が含まれることはなく、またその産業の中には情報、広告、金融業界などは含まれないとさ
れていた。最近になってなぜビジネス方法が特許として認められるようになったいきさつやなぜ必要な
のかということを、特許制度、特許権やこれまでの特許の歴史を踏まえた上で見ていきたいと思う。
(1) 特許制度
まず、最初に発明に対する特許を制度として世界に確立したのは、1474年のヴェニス共和国(現・ヴェ
ネチア)の特許法だと言われている。それは新規な機械を発明し、届け出たものに対して10年間その構
造に対して保護を与えるというものであった。それから、イギリス、ヨーロッパ大陸さらにアメリカに
渡り、世界へと特許制度は広がっていった。日本での特許制度の始まりは明治4年(1871年)制定の専売
略規則というものである。しかし当時は技術や人々の意識は制度が必要なほど高くなく、また審査体
制も不十分であったため、この規則は翌年に廃止された。それから明治18年(1885年)になり国内の発
明者に対しての保護の要求が増加、不平等条約の改正やパリ条約の成立などといった国際情勢の動き
とともに専売特許条例が制定された。その条例の内容はアメリカ法とフランス法を基礎に、特許要件
の法定(新規で有益な事物の発明)、先発明主義、特許権の存続期間(最高15年)など全26ヶ条からな
るものであった。
その後、産業発展に伴い何度も特許制度は改正され、第一次大戦後の産業発展、大正デモクラシー
の影響で大正10年に特許法が大きく全面改正された。これが昭和32年に施行された現行法になるまで
の40年間効力をもっていた旧法であり、現行法の基本骨格ともなっている。この法律ではそれまでの
先発明主義を廃止し、ドイツ法を基本とした専願主義が採用され、他にも出願公告・異議申立制度、
無効審判請求の除訴期間(5年)、再審制度などが新しく加わった。そして第2次世界大戦前後の情勢
変化や産業発展に伴い、昭和34年に全面改正されたのが、現行法である。この中に新しく加わったの
はは発明の進歩性が特許要件になり、特許権の効力は産業上利用できるものであるということの規定
や特許権の存続期間を出願日から20年超えないものとすることなどである。
このように日本では明治時代から特許制度はあり、何度も改正をしながら発明品が守られてきた。
特許制度がなければ発明は第三者にも自由に使えることができ、わざわざ開発しなくとも真似すれば
いいというようなことにもなりかねる。産業発展するためにはこの特許制度は必須になり、毎回改正
している時期が産業発展の時と重なっているのはそのためであり、違う形で産業発展していくのでそ
れに合わせているのがわかる。
(2) 特許の条件
では、どんなものに特許を与えられるのだろうか。前にも触れたように特許とは「産業上利用でき
る発明」を保護するもので、発明は特許法第2条第1項にて【自然法則を利用した技術的思想の創作
のうち高度のものをいう】と定義されている。この他にも特許となる条件がある。「新規性」と「進
歩性」である。
「新規性」はその発明が新しく、今までに公開されていないものということである。特許出願する
までに公に発表などしてはならず、秘密にしておかなければならない。また、「進歩性」はたとえ新
規性が認められたとしても、簡単に思い付くようなものは進歩性が無いと見られる。
やはり特許はさらに産業発展するためにあるものであって、簡単に思い付くものを特許にする
のではその役目は果たせないことから、進歩性は重要となってくる。
(3) ビジネスモデル特許とは
では、ビジネスモデルとは何か?ビジネスモデルと一言でいっても、広い定義がある。
<ビジネスモデルの本質>
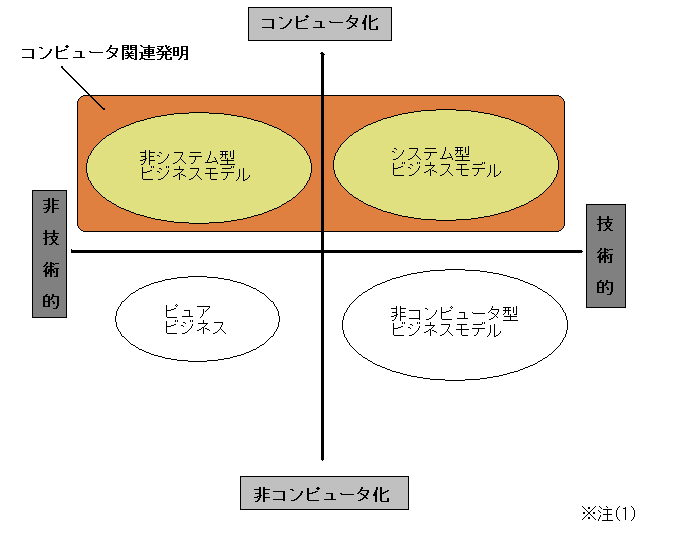
ビジネスモデルは主にこのシステム型ビジネスモデル、非システム型ビジネスモデル、非コンピュ
ータ型ビジネスモデルなどに分けられる。そのうちのシステム型ビジネスモデル、非システム型ビジ
ネスモデルはコンピュータ関連発明といわれている。
それぞれのビジネスモデルとは、
・システム型ビジネスモデル…ハードウェア依存型のビジネスモデル。例えばFDに記録されたプロ
グラムがパソコンでかな漢字変換を実現した特許などがある
・非システム型のビジネスモデル…金融関連のビジネスモデルや電子商取引のビジネスモデル等を
示す
・非コンピュータ型ビジネスモデル…コンピュータやインターネットを使わなくとも可能なビジネ
スモデル
である。
例えば日本で特許を取った“オートカフェ”という「来店した客が自動食器貸し機に硬貨を投入し、
食器を借り受け、その器に飲食物供給装置より飲食物を入れ、テーブルに運んで飲食するようにした自
動飲食物店」というものである。この機械一つで喫茶店の役割を果たすというこの商品は、飲み物の自
販機のような単にボタンを押すと紙コップの中に飲み物が入るというものではなく、食器が出てくると
いうことでリサイクル時代の現在に合っている点から“新規性”が認められたと思われる。コンピュー
タもインターネットも使わずとも認められたビジネス特許である。
主に日本ではビジネスモデル特許はシステム型ビジネスモデル、非システム型ビジネスモデルをコン
ピュータ関連発明として審査が行われているが、非コンピュータ型ビジネスモデルの例のようにコンピ
ュータやインターネットを使うものだけがビジネスモデル特許として認められるというわけではない。
(4) ビジネスモデル特許が認められるまで
前に述べた事例が前々からあったにもかかわらず、最近になってビジネスモデル特許について何故騒
がれているのかというと、アメリカでは1908年にビジネス方法の特許出願をしたところ認められなかっ
た例からビジネス方法には特許の対象とならないという考えがあったからである。その概念を初めて打
ち破ったとされるビジネスモデル特許が「ハブ・アンド・スポーク特許」である。
まず「ハブ・アンド・スポーク特許」とはシグネチャ・ファイナンシャル社の投資信託の運用方法に
関する特許で、ハブとスポークということで自転車の車輪とみたてている。(次項1−2参照)中心部
分にハブ、周辺の放射線状にスポークがあり、スポーク部分の複数の資金を真ん中のハブ(ポートフェ
リオ)の部分に集中してプールし、その資金などを株などの金融商品で運用して利益を上げるというも
のである。効果として資金の有効な運用ができる、管理費用が節約できる、節税できるなどがあげられ
る。
これについてステート・ストリート・バンク社はシグネチャ・ファイナンシャル社にライセンスの申
し入れをしたところ、交渉が決裂したためにステート・ストリートバンクは「このようなビジネス手法
は特許の対象にならない」と特許無効の確認訴訟を起こした。その結果、米地裁では「ハブ・スポーク
特許」は特許の対象外と判断され、特許は無効になった。
しかし、シグネチャ・ファイナンシャル社はCAFC(United States Count of Appeals for The
Federal Circuit;米連邦巡回区控訴裁判所)に控訴し、CAFCで特許の有効性が認められた。判決内容
は、単に抽象的なアイデアではなく、具体的で有用で実体的な効果があるというものには特許の対象に
なるということであった。またビジネスモデルだからといって特許の対象にならないということを明確
に否定する結果になった。これをきっかけにアメリカではビジネスモデル特許が話題となり、ビジネス
モデル特許拡大に拍車がかかった。








