3 特許権侵害の事例と課題
特許とは発明者に対して強力な独占実施権を保証することで、発明の過程での困難を乗り越える動
機づけを与え、また特許という権利をもとに、特許をもとにした事業を興すための資金集めをしやす
くもする。しかし、このような魅力ある点ばかりが特許ではない。
特許を認められた発明者が権利を独占し、高額の特許実施料を課すようなことがあれば、その特許
をもとにして作られた商品はコスト高になり、その不利益は消費者に及ぶことなる。また、特許が権
利化されているとは知らずに、特許と同じ方法で事業を行っていたものが、後になって特許侵害を通
知され、知らずに実施していた期間についても実施料を請求されるということも起こる。
2で述べたように住友銀行の入金照合サービスでも、富士銀行、あさひ銀行、第一勧業銀行が特許
庁に異議申し立てをしている。三行は自らが提供する類似サービスの継続に支障がでる可能性がある
として特許の無効を訴えている。このように日本でも特許権侵害の事例が出てきている。そこで一つ
特許権侵害の事例を挙げる。
(1) 事例:プライスライン社の「逆オークションの仲介システム」
1999年10月13日、航空券のチケット、車やホテルの予約をWeb上で行っているプライスライン社がパ
ソコンのOSなどで世界最大のシェアをもっているマイクロソフト社を特許権侵害でコネチカット州の連
邦地裁に提訴した。プライスライン社によれば、マイクロソフト社の旅行サイト(Expedia.com)の利
用者に希望宿泊施設紹介サービス(Hotel Master)がプライスライン社の持つ特許を侵害していると
いうことであった。
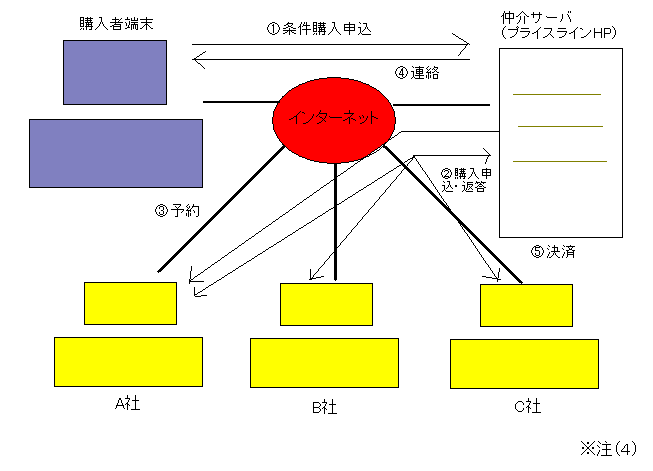
どのような特許かというと、消費者が購入条件を指定する逆オークションの仲介システムに関する
特許である。この特許を説明する上で航空券の購入の場合を例とする。
航空券チケットを買いたい人が仲介サーバ(プライスラインのホームページ)にアクセスして、例え
ば“東京からロンドンまでの往復チケットを3000ドルで買いたい”というように出発地、目的地、日時
などの他、希望価格を指定して、チケットの購入の申し込みをする。この際、併せてクレジットカード
の番号も明示する(①)。購入申し込みを受けた仲介サーバはこれを複数のチケット販売業者にこの条
件を転送する。するとA社は“2980ドルで販売する”、B社は“3050ドルで販売する”、C社は“3100ド
ルで販売する”と返答してきたとする(②)。この場合条件に合うのは、A社なので仲介サーバはA社に
予約を入れる(③)。ユーザーの条件に合った商品を選択したことをユーザーに連絡する(④)。仲介サー
バは購入者のクレジットカード番号を用いて、A社の航空チケット購入の決済を行う(⑤)。
このように、このシステムではユーザーが価格を指定して、複数の販売者に提示するという、購入
者主導のオークションである点に特徴がある。また、仲介サーバはクレジットカード番号を特定した
支払いIDを使用して支払うので、ユーザーによる「ひやかし」を防止している点にも特徴がある。
このマイクロソフト社の旅行サイトExpedia.comがプライスライン社に特許権侵害で訴えられた事件
で特に問題となっているのは指定条件に合ったホテルが見つかった場合、ユーザーのクレジットカード
に課金するシステムである。プライスライン社によると、同社はこの課金システムに関して特許を保有
している。さらに、特許権を有するアプリケーションから技術を盗んだマイクロソフト社の行為は、コ
ネチカット州法の不正商取引法に触れているとも主張している。またプライスライン社は株式公開の前
にマイクロソフト社と何度か話し合いを持ち、両社は業務提携に向けた交渉にあたって、その過程でプ
ライスラインは自社の技術を守秘業務契約のもと、マイクロソフト社に提示したという。このときにマ
イクロソフト社は情報をもとに技術を盗用したとプライスライン社が主張している。
(2) 特許権侵害についての課題
発明者の中には、分割出願や継続出願によってわざと特許成立の時期を遅らせる者も多いようである。
そうすることによって、知らずに特許を侵害していた者に対して、多額の実施料を請求することが
できる。こうした特許を「サブマリン特許」という。その典型として、出願から22年たって認められ
たコンピュータ関連の特許や、28年かけて認められた気体レーザーの基本特許などが挙げられる。そ
れとは知らずに特許技術を使っていた会社は多数に上り、そのような会社はこれまで使っていた技術
が突然使えなくなったり、巨額の損害賠償を求められるといった事態になった。
日本では“先出願主義”であるため、誰よりも早く特許庁に発明を出願した者が特許権をもらえる
が、アメリカの特許制度は“先発明主義”である。特許を持っていても他の企業が先に発明していた
ということが証明できれば特許無効も有り得る。また日本では出願公開制度があり出願してから18ヶ
月後に出願された特許内容が公開されるが、前にも述べたようにアメリカでは公開制度がないためサ
ブマリン特許の問題は頻繁に起こっていた。さすがに長い間サブマリン特許が潜んでいることは適当
ではないということでアメリカでも出願から20年で存続期間が切れるという歯止めがかけられた。ま
た、1999年末の特許法改正で、アメリカにも出願公開制度が導入された。しかし、これには例外とな
る条件が広く、公開制度としては不十分なものといわれており、まだまだ問題が残っている部分が多
い。








